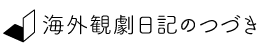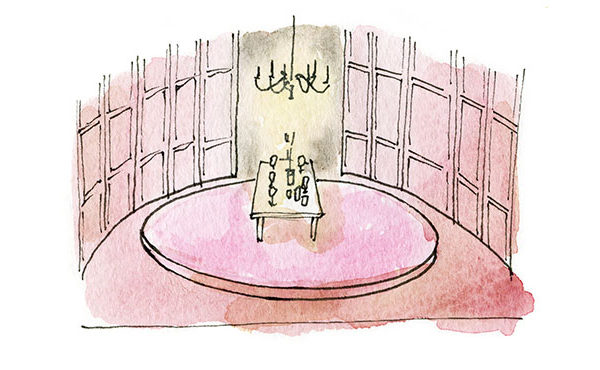以下は、旧ブログに2016年4月に投稿したものの転載(一部修正)。今見るとキャストがめちゃくちゃ豪華。
Sweeney Todd (London Coliseum)
5,10,11/April/2015
出演:Bryn Terfel, Emma Thompson, Philip Quast, Katie Hall, Matthew Seadon-Young, Jack North, John Owen-Jones, Alex Gaumond, Rosalie Craig他
演出:Lonny Price 指揮:David Charles Abell
薄々お気づきの方もおられるかもしれないが、1年前のプロダクションの感想である。当時書いていた感想を少し修正してアップしておくが、なぜこんなに放置してしまったのだろう…。
2週間だけのウエストエンドのお祭りプロダクション
スウィーニー・トッドは2008年にジョニー・デップ主演でディズニー映画化されたので、ご存知の方も多いだろう。18世紀フランスの怪奇小説に登場する「悪魔の理髪師」を主人公にした、ソンドハイムのミュージカル。
私はNPH(ニール・パトリック=ハリス)のファンなので2001年のコンサートバージョンの映像は見たことがあるが、ミュージカルとして上演されたものは見たことが無い。
今回のプロダクションは、2014年にNYリンカーンセンターで好評を博した同じくコンサートプロダクションの再演だ。主演のブリン・ターフェルとエマ・トンプソン、フィリップ・クワストが続投、ロンドンではジョン・オーウェン=ジョーンズ、ロザリー・クレイグなどがキャストに加わった。
劇場はイングリッシュ・ナショナル・オペラのロンドンコロシウム、舞台上にはフルオーケストラに加え、アンサンブルが数十人。豪華キャストによる2週間だけの期間限定上演であるということ、チケット価格(最高155ポンド)の高さも相まって、ウエストエンドのお祭りのようなプロダクションだった。
プリンシパルロールには他にアレックス・ゴーモンド 、ケイティ・ホール、マシュー・シードン=ヤングなど、役名の無いアンサンブルにもミュージカル好きなら見覚えのある面々が多かった。
オーケストラを組み込んだ舞台演出
演奏は舞台上でフルオーケストラが担当する。前方に弦楽器、後方は管楽器を左右に振り分け、オーケストラの周辺に通路と舞台を設け役者が行き来できるつくりになっている。
舞台セットは照明や垂れ幕以外は理容用小物程度、多くをオーケストラの楽器や劇場にあるものを借りてきて代用するという演出になっていた。舞台上に常にいるオーケストラを取り込んでうまく芝居を作り上げていたと思う。コントラバス奏者のスツールをエマ・トンプソンが取り上げて使う、ピレリのサクラの客は長髪の打楽器奏者、アンソニーの旅行かばんは楽器ケース、といったような演出があるたびに見ていてニヤリとしてしまう。
オープニングでは、オーケストラの正面に並んだ譜面台の前に正装したプリンシパルの役者たちが楽譜を持って舞台上に登場する。なるほどそういうスタイルのコンサートプロダクションなのか、という予想を裏切り、1曲目スウィーニー・トッドのバラードの途中で突然ターフェルが苦い顔で歌をやめ、楽譜を床に落とす。他のキャストも次々とそれに続いて楽譜を放り出し、険しい顔で拳を振り上げ踊りながら続きを歌い出す。
アンサンブルは舞台上を走り回り、舞台上に飾られていた花を床に倒し、自らフォーマルな衣装を破き、オーケストラ正面のピアノをひっくり返して分解してしまう。キャスト達は役に見合った衣装をつけて再度舞台上に登場し、スウィーニー・トッドのバラードを歌い終える。
これはただの上品でお行儀の良い退屈なコンサートプロダクションではなく、不穏な物語の始まりだということを強烈に示唆する演出であった。
恐怖感に欠けるコメディ色の強いスウィーニー・トッド
しかしそれに反して、今回のプロダクションは芝居全体を覆うべき不穏さ、怖さには欠けるものだったと言わざるを得ない。この芝居の中心はエマ・トンプソンで、彼女が舞台上に出てくるたびに全ての注目と笑いを攫ってしまう。コメディの要素が強く笑いの多いプロダクションだった。
ブリン・ターフェルの歌唱力はもちろん申し分ないのだが、演技自体にはもう一歩凄みや迫力が欲しい。周りのミュージカル役者たちは非常にいきいきとしているのに対して、彼からはあまり迫ってくるものがなく、不当に長く苦しめられた過去や連続殺人を犯すにいたる狂気をあまり感じとることができなかった。表情の変化が少ない顔立ちだからだろうか。
また常に演奏中のオーケストラが目に入ること、舞台装置や衣装がほとんど作り込まれていないといった要因のために、物語にのめり込みにくかったのかもしれない。
芝居後半には、スウィーニー・トッドの理髪店のためにミセス・ラヴィットが誂えた椅子が登場する。カミソリで喉をかき切られた不運な客を階下へ効率良く廃棄(もしくは配達)するために特別に誂えられたものだ。この殺人のための椅子が運び込まれ、覆っていた布をサッと取り払うとコロシウム劇場の客席の椅子とそっくりなデザインの椅子が現れる。このシーンで全くゾッとしないことが今回のプロダクションが芝居の本質的な恐怖感を煽ることに失敗していることを象徴していると思う。
私が一番ゾッとしたのは、トビーがミセス・ラヴィットとトッドの行いにようやく気がつく最後の場面だった。生理的な嫌悪感と、最終的に精神のバランスを崩してしまうところが痛々しい。
コンサートプロダクションならではの丁寧な音楽演出
フルオーケストラ演奏とアンサンブルの厚みのおかげで、音楽的にはとても充実したものだった。上演時間が長めで、おそらく演奏テンポもゆっくりめでかなり丁寧だったように思う。ターピンへの手紙のシーン、アンサンブル5人による合唱が上手いことが印象的だった。1箇所アルトとソプラノの音があたる和音があるのだが(♪Johannaのところ)、どちらの音量もほぼ同じくらいに目立たせカッチリと不協和音を響かせるという好ましいバランスだった。(根音を目立たせ、あたる方の音はまわりに隠れるくらいの音量に抑えてしまうというバランスをよく聞くので。)
ブリン・ターフェルとフィリップ・クワストの組み合わせはよく合っていたし、エマ・トンプソンの歌も物足りないということは無かった。
一番意外だったキャスト、ジョン・オーウェン=ジョーンズのピレリだが、最近では珍しいコミカルな脇役を非常にいきいきと演じていたのを見れたのが嬉しかった。歌はもちろんうまいし、とても若々しく見えた。
私がソンドハイムの曲の中で一番好きな”Not While I’m Around”のパフォーマンスは私好みで気に入った。若手ジャック・ホワイトの実直な歌い方が愛らしく、毎回涙ぐんでしまう。
ロザリー・クレイグのよく目立つシャープな歌声も乞食役の曲調にぴったり。上手い配役だと思う。
私が贔屓にしているマシュー・シードン=ヤングは歌も良い体躯の好青年という雰囲気も良かったが、Urinetownに引き続きどことなくオタクっぽさがにじみでてしまうところが新鮮なアンソニーだった。メガネのままだからだろうか。彼は普段からメガネ文系青年っぽい雰囲気だが、こういう役でメガネ着用というのは珍しい。私は彼のメガネのファンなのでステレオタイプに抗う感じが好ましいなと思った。
ビードル役アレック・ゴーモンドもDirty Rotten Scoundrelsから安定してねっとり気持ち悪かった。(※悪口ではない)
こんなところだろうか。
そこまで大好きなプロダクションにはならなかったが、全体的にはとても楽しいイベントだった。