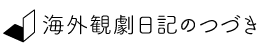ウエストエンドで上演されたAn American in Parisの上映用映像を先日ようやく見た。とても良かったので、舞台鑑賞時との印象の違いと、さらに映画と舞台の違いについて、感想を書いておく。ネタバレあり。
概要
本作は、映画『巴里のアメリカ人』(1951)の舞台化作品である。パリとブロードウェイ上演が高評価を受け、主演俳優二人を伴ってロンドンでも上演された。さらに、ロンドン公演のオリジナルキャストの録画映像が、2018年に映画館で上映されており、現在はBroadway HDなどで鑑賞できる。今回は、この映画館用映像を中心に感想を書いていく。
音楽:George Gershwin, 詩:Ira Gershwin
舞台脚本:Craig Lucas, 演出・振付:Christopher Wheeldon, 美術:Bob Crowley, 映像:59 Productions
出演:Robert Fairchild, Leanne Cope, Zoe Rainey, David Seadon-Young, Haydn Oakley, Jane Asher ほか
感想
舞台鑑賞時と比べて
私は、オリジナルキャストのロバート・フェアチャイルド(ジェリー役)の契約が終わり他の俳優にバトンタッチしたあと(2017/7/31)観劇していた。彼以外はオリジナルキャストで鑑賞していたのだが、今回鑑賞した上映版は、こんなに違うか、と驚くほど別物だった。
映像を見てわかったことは、この物語は、恋人たちジェリーとリズのケミストリーと、ジェリー役を誰がやるかがとても重要であり、ジェリーが唯一無二のパフォーマーでなければ、恋が実る結末に至るストーリーが機能しない、ということだ。
私が見た舞台では、申し訳ないがジェリーの魅力がよくわからず、アンリの方が魅力的に思えた。その他のアンサンブルと区別がつきにくかったので、ダンスで物語を追うのに苦労した。
比較すると、当時ニューヨーク・シティ・バレエ団のトップダンサーだったロバート・フェアチャイルドは申し分なかった。彼のためにこの舞台版ジェリー役が形作られたように思える。チャーミングで、素人目にも踊りが抜群で、一歩目から目が離せない。シルエットだけでもパッと目立つ。歌もうまい。ブロードウェイで数々の賞に輝いたのも納得だ。
リズ役のリアン・コープも、フェアチャイルドと踊っている時の方がミステリアスで魅力的に見えた。これも、お互いに引き立てあえる技術や相性の良さがあるように思えた。
映画と舞台を比べて
映画から舞台にするにあたり、プロットはかなり変更されている。私個人はあまり映画に思い入れはないからかもしれないが、それぞれの変更点は舞台上演のためには必要な変更に思え、随所に工夫が感じられた。
舞台のプロットは、映画の印象的なセリフと音楽をなるべく活かしながら、メインの男性三人(ジェリー、アンリ、アダム)と女性二人(リズ、マイロ)が様々な場面で関わりあうように整理し直されている。映画で印象的だった「あの」ポーズは最後まで見せずに観客を焦らし、幕が降りる直前に美しく再構築される。
舞台が映画と大きく異なるのは、リズをバレエダンサーを目指す香水の売り子に、フィナーレのダンスシーンを新作のバレエ公演という設定にした点だ。彼らの多くはまだ夢を追う途上で、このバレエ公演を目標とする成長物語としても楽しめる。メインの5人それぞれに複数の会話シーンや見せ場が用意され、バレエ公演の前後に皆の音楽・感情的クライマックスが頂点に到達する。全員の心情を表現できる脚本により、物語展開の理由づけがよりはっきりと示され、葛藤が十分に表現されるようになった。
特にアンリが歌うI’ll Build a Staircase to Paradiseで描かれる世界は、映画の何倍も重層的だ。アンリは映画と比べてかなり良い役になっており、物語の展開に重要な役割を果たしている。
語り手を作曲家のアダムにまとめたところも良いと思った。舞台版では彼もリズに恋心を抱くようになるのだが、アダムがストーリーの舵取りをすることで、フィナーレの哀愁が強く印象付けられる。「あなたは私のパリのアメリカ人よ」という台詞は予想外だったが、そこからジェリー、アンリ、アダムが歌うThey Can’t Take That Away From Meの流れは感動的だ。
映画は、良くも悪くもジーン・ケリーというスターの主演映画であるという側面を無視できない。しかし現代の舞台で、ケリーのスター性を再現することはおそらく不可能だろう。舞台では映画をそのまま再現するよりも、アンサンブルワークとして組み直し、芸術の祝福、友情と愛の物語であるというテーマを強調する方向性がとられている。
さらに映画と大きく印象が異なるのが、戦後すぐのパリというバックグラウンドに、よりダークな雰囲気を選択している点である。ナチスのシンボルやリズとアダムがユダヤ人であるということが折に触れ強調される。とくにリズは冒頭から登場し、ナチス占領下のフランスの悲しい記憶を体現する存在として描かれる。それにより、なぜ彼女が運命の恋に落ちるべき相手なのかが間接的に表現されている。
デザインと出演陣
また、ボブ・クロウリーと59 Productionsによるセット、衣装、映像デザインが素晴らしく、劇のもう1人の主役であるかのようだ。デッサン風ムービー、印象派絵画や抽象絵画など、パリで花開いた様々なスタイルを贅沢に欲張りに取り入れながらも、下品にならず、優雅にパリの街並みやダンスの動きを表現する。
それぞれのキャラクターが好ましい人物として描かれ、特にメインの女性二人の描かれ方が時代にあわせてアップデートされているのが良い。リズは一人で登場し、ジェリーと対等に対話するし、マイロのストーリーラインも整理されて、ジェリーとの恋の駆け引きもお互いフェアに見える。マイロは映画よりもさらに分別のついた大人の振る舞いをするのだが、そこに葛藤が見えるのが切ない。また曲が与えられたおかげでゾーイ・レイニーの歌唱力も十分にアピールできている。
主役のジェリーも舞台の方が理性的だ。先にも書いたが、フェアチャイルドはバレエも歌もうまいので、彼をキャスティングできたことがこの舞台の成功の大きな要因だろう。アンリを演じたヘイデン・オークリーの優しげな雰囲気、大人っぽさもうまく機能している。私はアサシンズ(2014-5)以来、デイヴィッド・シードン=ヤングの恋する役が好きなので、再びちょっとシャイで、さらに心優しく切ないアダムを見ることができて、ファンとしては嬉しかった。
主演2人のダンスと何十人ものアンサンブルの振り付け、時間経過や場面転換の手際も洗練されている。映画とかなり様子は変わっているが、舞台はより大人の物語に書き換えられ、21世紀の観客の共感を得やすいプロダクションに昇華されている。