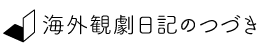DULL-COLORED POP 『福島三部作 一挙上演』
(in→dependent theatre 2nd)
2019/9/2
作・演出 谷賢一
友人の勧めで、DULL-COLORED POP『福島三部作』を大阪で鑑賞してきた。各2時間程度の劇を3作続けて見たが、そこまで疲れることもなく、大変面白かった。
あらすじやキャストなどは公式HPにも詳しく掲載されているので省くことにして、鑑賞後に書き始めた感想をまとめておこうと思う。
第一部 1961年:夜に昇る太陽
福島県の双葉町で原発誘致が決まる前の数日間が描かれる。実際に福島に原発が立つことは承知しているし、筋の予想はつくのだが、その成り行きが見応えのあるドラマに仕上がっている。
主人公は農家の長男の孝。東京の大学で学んでいるが、実家のある双葉町に帰省したタイミングで、町に見知らぬ人々が訪れる。孝を含む三兄弟が微笑ましく可愛い。この三人を可愛く思えることが、三部作を見通すためには必要不可欠だ。 祖父と母と兄とで話は展開できそうなのだが、やや浮ついたような性格の次男・忠だけ妙に造形が複雑で、彼が意外と作者の代弁をしているのではと感じた。
ストレートに作ってあるような印象だが、話の作りも演出も洗練されている。
子供たちのパペットを登場させるのも、幼稚なようで全くそうではない。観客がパペットに慣れた頃に、パペットと俳優の入れ替わりなどで笑わせる等のメタな演出を入れるのも手堅い。
とてもうるさい大声演技も、それが心地よく、青春真っ只中の若者の葛藤と相性が良い。
背後のスクリーンに、黒い背景に白い文字で説明がつく場面がとても多い。事務的な画面で、雰囲気は盛り上がらない。全体的にシャウトや音楽など音の情報量が過多なため、合間の文字のみ説明で緩急がつくだろうか。
約2時間と長くはない芝居で、何度も「50年後には」という発言が出てくる。その度に、2011年に福島がどうなるかを観客はリマインドさせられる。このとき、50年後にかける期待と現実の落差が切なさを生むよりも、観客が何度も近年の出来事を思い返し、物語に没入しすぎない効果を生んでいたように思う。
私はある程度それを忘れていたころに思い出させてくれる方がドラマチックになると思うのだが、字幕の頻度や情報量といった、ドラマチックになりすぎない演出が、家族ドラマや青春ドラマ風の王道ドラマチックな部分とのバランスを取っている。
第二部 1986年:メビウスの輪
三部作の中でも、第二部は疾走感があり、短く感じた。
一人の男が、自分の発言の重さ・責任と信念とのあいだで苦しむ。
第二部の主人公なので、第一部に忠がいるのは当然だったのか。ウクライナでチェルノブイリの原発事故が起こったそのとき、福島県双葉町の町長を務めている。
第二部ではペットの犬が語りを担当するが、回数も分量も多い。合間に亡き王女のパヴァーヌに合わせて踊ったり、哲学的解説を入れたりもする。この犬の冒頭の場面は涙無くしては見れない出来で、犬の存在が劇全体をまとめつつ、人間ではない生き物の視点で地上の人々が認識しない次元にも話を発展させてしまう。主張の強い異色のナレーターだ。
また、悪魔のように顔や性格を変えながら主人公を誘導する男・吉岡も重要な役割を果たしている。吉岡は、大人の立場や責任や世論への影響などの概念を凝縮したような存在で、主人公を追い詰める。非常に礼儀正しいはずの彼のアジテーションが苛烈になり、ついに靴を投げつけるところではおもわず笑ってしまった。
テンションが最高潮に達して始まる歌唱シーンは、演劇的に高められた素晴らしい場面だった。不思議な男吉岡や、喋って踊る犬に、わざと大仰な演技をして歌舞伎の見得を切るようなしぐさなど、二部はファンタジーのような雰囲気がある。そのため、音楽シーンの挿入もさほど違和感がない。政治家にビジュアル系メイクを施すのも、そのあと施したままであるのも、人物の内面と外面との対比を強調する良い効果があったと思う。
演技で最も印象深かったのは、第二部ラストの主人公の泣き笑いの顔だった。
第三部 2011年:語られたがる言葉たち
第三部のタイトルは、「語られたがる言葉たち」である。唯一好ましくないと思ったのは、冒頭の死者の「死にたくなかった」というセリフたちだ。実際に発せられただろう言葉が多いバーベイティム演劇的な作品のなかで、声なき死者の声を同時に代弁してしまうのはやりすぎではないか。第二部の犬の語りで死者の声について言及されるのが、第三部の冒頭につながり、フィナーレにも繋がっていく。しかし、第三部の冒頭では、「語らせる」言葉のルールからセリフが逸脱しているように感じた。
第三部は、かなり直接的な描写で3.11と福島の傷を語る。演劇でしかありえないような大仰な演技や展開は少なくなり、ドキュメンタリーのような感触だ。いっそ乱暴な演出であるように感じる。第一部と第二部の演劇的な表現は、ある意味オブラートに包むような手法だったのだろうか。
三兄弟の三男・真が主人公に据えられるが、彼は多くを語らず、部下のジャーナリストや住民たちの声の方が多く耳に入ってくる。
自分勝手で耳障りな言動が多く、端から見ているとイライラさせられるが、最後の場くらいになると、震災と原発事故による痛みの前に、個人個人の態度などは致し方のないものに思えてくる。
取材で収集した様々な声を、劇場用に加工しすぎず生々しく再現しようとしている演劇は、ワークショップ的雰囲気もある。事態がまだ収束していない現在、記憶が風化する前に舞台にかけるため、やや演劇の型にはまりにくい。いや、型にはめることを積極的に避けるべき題材なのかもしれない。
第一部から感じていたのは、鑑賞者である私の、福島との距離である。
第三部では、ニュースの向こうの被災した人々の苦しみが、生の俳優の演技を通して全く違う感触で迫ってきた。無関心なつもりもなかったが、震災で被災したことがない私は、よっぽど気楽にこの芝居のチケットを買って劇場にやってきている。
私の生業がもし作家だったとして、この物語を作る覚悟も、福島で上演する覚悟も自分には全くない、ということが最も重く心にのしかかるように思えた。