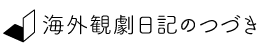骨と十字架(新国立劇場 小劇場)
Keep Walking
2019/7/20
パラドックス定数の野木萌葱による新作。パラドックス定数は、『ブロウクン・コンソート』と『トロンプ・ルイユ』を見たことがあるが、今回は劇団員の出演ではなく、演出も新国立劇場演劇芸術監督に就任した小川絵梨子である。友人のすすめでチケットを購入。
イエズス会の司祭でありながら、古生物学・地質学者であった、ピエール・テイヤール・ド・シャルダン(1881-1955)が主人公。キリスト教的進化論を唱えるテイヤールの学術活動に検邪聖省(かつての異端審問所)から圧力がかかるところから物語は始まる。
出演:神農直隆、小林隆、伊達暁、佐藤祐基、近藤芳正
美術:乘峯雅寛、照明:榊美香、音響:福澤裕之、衣裳:前田文子
感想(ややネタバレ注意)
異端審問と聞き、最初に思い描いていたのはショーの『聖ジョウン』だった。しかし『骨と十字架』の舞台上の彼らは、会話を重ね意見をぶつけ合うものの、言葉の応酬自体に熱心なわけではなく、議論自体をエンターテイメントとして期待していると物足りなさを感じる。何を言うか言わないかが問題だと言いながら、うっかり口を滑らせすぎる。
しかしそのぶん、熱意と感情は有り余るほど感じ取れ、見応えはある。鑑賞しながら「いやはや熱血だなあ」「ロマンティックなことを言うではないか」などと思ってしまった。熱血ロマンティック会話劇である。思い返せば、野木作品は私からすれば毎回熱血ロマンティックである。
(ちなみに、もしこれをパラドックス定数で上演していたら、もっと演技がドロドロしていただろう。)
登場人物の中では、司祭で学者のリサンが今どきの科学観をもち、教会と科学を別物として認識しているため、私は彼に心が寄せやすかった。
主人公のテイヤールも、今となっては常識である進化論を唱えたかどで教会から介入されるという設定なので、まっとうな人物なのに不当な扱いを受けているように私の目には映った。しかし彼は、劇の最後には人間が神に進化していくという思想に辿り着いており、言葉の端々に狂気じみたものを感じる。彼が今の科学者ならデザイナーベビーの推進をしていそうだ。
もはや遺跡のように朽ちかけたヨーロッパの教会建築と、中国の岩場の発掘現場が両立される舞台装置は面白い。ほとんどの芝居は客席側に長く張り出した部分で行われるが、この長さと客席近くの段差が活かしきれていたかどうかは疑問で、建物の外と中が何度も切り替わることは展開で理解できるが、視覚的には表現しきれていない。『1984』の時にも感じたが、演出の小川は視覚を用いた意味づけにさほど興味はなさそうだ。
感情のすれ違い、主張の食い違いについて見ていく芝居は面白かったのだが、フィナーレはやや劇的効果に欠ける気がした。この芝居の後半は35分程度と短く、ターニングポイントやクリティカルモーメント−−後の展開が決定的になる瞬間、その引き金となる発言、行動などをそう呼びたい−−がひとつに定まらない。様々な人が行ったり来たりし、様々な組み合わせで会話をしており、明確な山場がない。私は「ここぞ」というモーメントの提示があってこそドラマだと感じるから、テイヤールが信仰の危機を乗り越える瞬間とその理由を明確に示すくらいやってみても良かったと思う。
この芝居はかなり好評だ。なので、これは私ぐらいかと思うと恥ずかしいのだが、実を言うと、テイヤール自身が信仰の危機を乗り越えたきっかけと、その危機の前と後の思想がどう異なるのかがよく分からなかった。
文字で戯曲を読めばもう少しきちんと前後が理解できるような気もするので、各場面の長さと動線設計の問題か、進化論の内容に気を取られすぎたためか、もしくは受け手の私が大雑把な無宗教者だというあたりに、私の理解不足は起因するのだろう。
俳優は概ね好ましく見たが、イエズス会総長役の小林隆の演技の明快さが抜きん出ていた。
『骨と十字架』は、新国立劇場で7月28日まで、兵庫県立芸術文化センターで7月31日に上演。